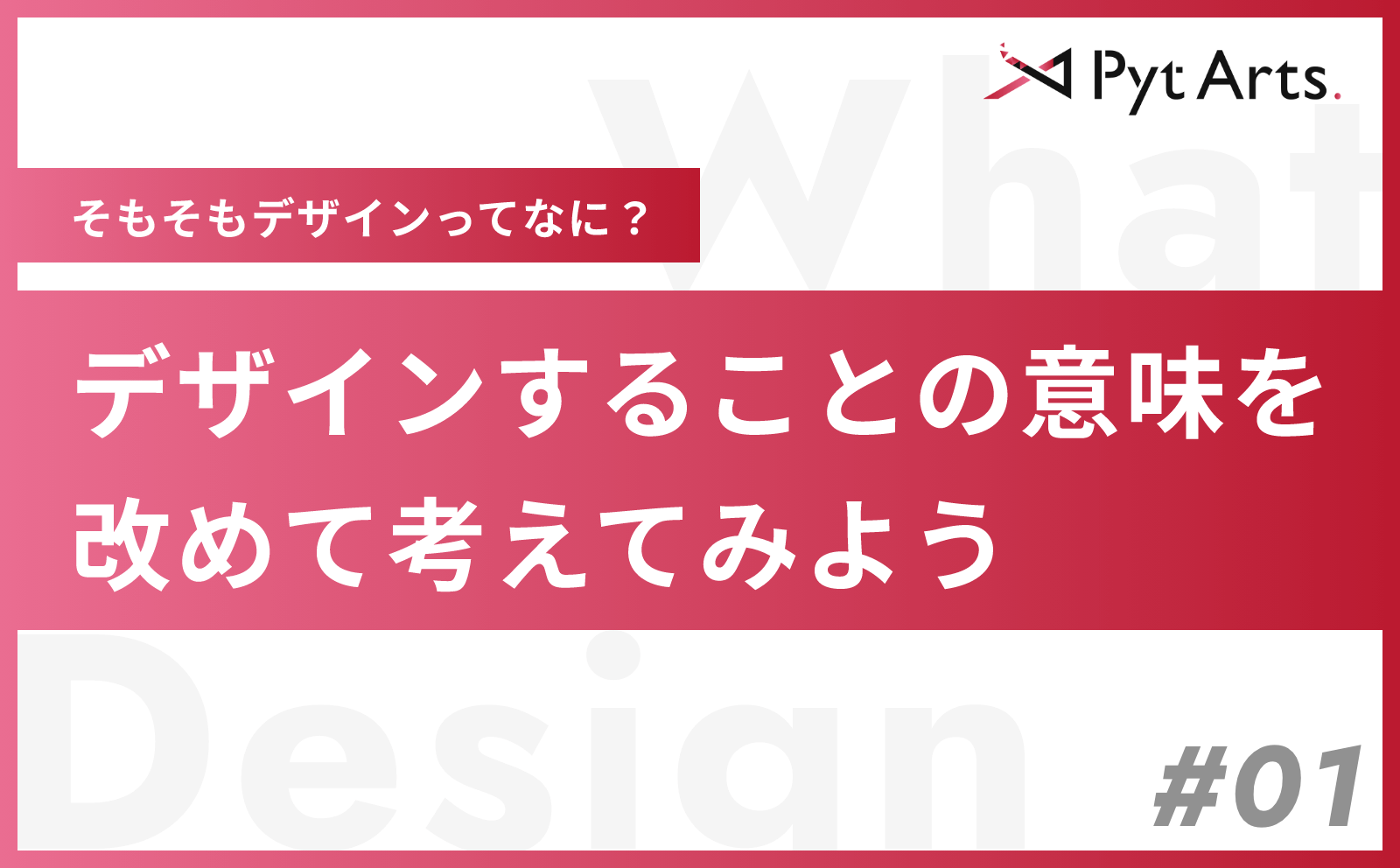
みなさんこんにちは!PYT Artsデザイナーの田中です。
いきなり質問ですが、みなさんはデザインと聞くとどんなことを想像しますか?
非デザイナーの方や初心者の方の中には「イケてるビジュアルを作ること」と考える方もいるのではないでしょうか?
そこでPYT Artsのオウンドメディア初投稿となる今回はそもそもデザインとは何か、デザインする意味とはなんなのかについて解説していきます。
今回の記事を読むことでデザインの意味を改めて考え直すことができ、その結果クライアントワークにおいて最適な提案ができるようになります。
それでは始めていきましょう!
デザインという言葉はもともとラテン語を語源とした言葉になります。
元の意味は計画したことをアイコンで表現することだそうです。こう聞くと設計書の方がイメージが近いかもしれませんね。
そして現代へと時代が流れていくにつれて、デザインはより”人間社会”に溶け込んでいくようになり、「目的を見出し、その目的を達成する計画を行い実現化する。」という一連のプロセスへと落とし込まれていきました。
つまりはいけてるビジュアルを作ることだけがデザインではないということですね。
ではデザインの役割についてもう少し深掘りしていきましょう。
視覚言語とは書いて字の如く、”視覚を利用する言語”です。
人間が受け取る情報の約80%は視覚情報によるものと言われています。情報化社会において、視覚的なコミュニケーションはますます重要になっています。
そこで伝えたい情報をビジュアルで表現することで言葉で伝えるよりもより正確に、鮮明にメッセージを伝えることができるようになるのです。
アメリカのグラフィックデザイナーであるポール・ランドは、「デザインとは形(フォルム)と内容(コンテンツ)の関係のことだ」という言葉を残しました。簡単に言えば、「何」を「どのように」表すかでメッセージの伝達力は違うということです。
これは自然言語を用いた文章表現においても、視覚的イメージを用いた表現においても同じことが言えます。こうした基本的なコミュニケーションの仕組みを理解することで、デザイナーはより意図的にメッセージを設計することができるようになります。
ビジュアルコミュニケーションの詳しい内容についてはプラット・インスティテュートの助教授である遠藤大輔さんがSchooにて動画授業を行なっていますのでぜひご覧になってみてください。
https://note.com/dtp_tranist/n/n021f9c6c3f7c
2つ目のデザインの役割としてVI(ビジュアルアイデンティティ)が挙げられます。
VIとは企業やブランドの価値、コンセプト、メッセージをビジュアルとして作成し、視覚を通してブランドイメージを伝える要素のことです。
主にブランディングなどで活躍する知識になります。
VIは、ブランドシンボル、ロゴ、色、デザインエレメント(ロゴやアイコン以外のグラフィックパターン)、指定書体のような素材などがあります。さらにそれらの素材を活用したWebサイト、宣伝・販促ツール、店舗内装・外装、商品パッケージ&紙袋、制服、名刺、封筒、パンフレットのような印刷物のデザインなども全てVIに含まれます。
つまりVIが適切でない場合、企業やブランドが設定しているターゲットとは違う層へのアプローチになってしまったり、間違ったブランドイメージを伝えてしまうといったことが起きてしまいます。
大抵、VIで失敗をする場合は、間違ったビジュアルを作成しまったのではなく、デザイナー側とクライアント側で伝えたいメッセージに相違がある場合が多い印象にあります。
ですので、VIとしての役割を最大限活かすにはクライアントを交えたワークショップ形式のミーティングを開催し、ブランドストーリーや、ブランドに対する想いなどを隅々まで聞き出し、本当に伝えたいことを見つけることが重要です。
よく初心者の方にありがちなのが、デザインとアートを混同させてしまうことです。
これまで記述してきた通り、”メッセージを伝える”という点ではデザインとアートは同じかもしれませんが、決定的に違う要素があります。
それは課題解決です。
アートは自己表現や問題提起といったようにメッセージが一方通行なのに対し、デザインは課題解決をするためのラリーが発生します。
どういったことかというと、デザインを行う流れは下記のように、「問題の発見」→「解決策の模索」→「具現化」→「経過観察」をぐるぐる回していきます。
つまりデザイナーがターゲット層から問題を受け取り、デザイナーからデザインという形で解決策を投じ、受け取ったユーザーが評価するというキャッチボールがうまれます。
これを理解することで自分の好き嫌いでデザインしてはいけないことの理由がわかりますよね。
ただし、デザインとアートをきっちりと区別しなければいけないというわけではありません。これは中級者にありがちな考え方なのですが、デザインとアートは違うという考え方が強すぎて頭が硬くなってしまい、表現の幅が狭くなってしまうことがあります。かく言う私も数ヶ月前までこの沼にハマっていました…
アートのような表現技法やアイディアをデザインにうまく落とし込むことができれば、それは唯一無二のVIになり、ブランディングとしての成功につながっていくでしょう。
いかがでしたでしょうか?
少し難しい話も混じってしまいましたが、これであなたはイケてるビジュアルだけを追い続けるデザイナーからは脱却しているはずです。
デザインすることの意味を正しく理解をし、目的の達成や問題の解決に大きく影響を及ぼすことのできる一流のデザイナーを目指して、共に頑張りましょう。
最後に私が大切にしている言葉を送らせていただきます。
「かっこよくてもデザインとしては失敗していることを疑え」
「ダサくてもデザインとして成功していればそれで良い」
要はかっこいいとかダサいとかは人それぞれの価値、感性で全く変わってくると言うことですね。
PYT Artsでは問題を抱えている企業、ブランド様へ向けてデザインという側面からサポートをさせていただいております。話だけでも聞きたいという方はお問い合わせフォーム、またはSNSのDMからお気軽にご連絡くださいませ。
以上、ここまで読んでくださりありがとうございました。
次回の更新もお楽しみください!
現在準備中です


